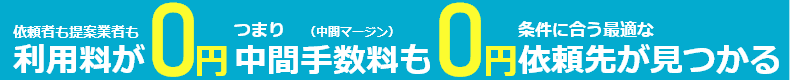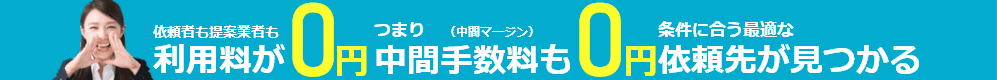障子枠の種類13選と障子紙の種類5選

障子は、日本古来の建具として現在でも見かける機会が多くなっています。一般的なイメージとしては、ごくシンプルなデザインのものだけが思い浮かびがちですが、実はその種類は多様です。障子枠も使われる紙も、思った以上にさまざまなバリエーションがあり、特徴に応じて幅広いシーンで取り入れられています。
本記事では、障子枠と障子紙、それぞれの種類の主なものをピックアップして紹介しますので、現在障子の交換や張替えを考えている方は参考にしてみてください。
障子枠の種類
組子のデザイン別の分類
荒組障子
「荒組(あらぐみ)障子」は、組子(内枠に組まれた細い桟木)の数を少なくしてある障子枠で、「荒間(あらま)障子」とも呼ばれます。障子枠としては、最も一般的な種類になります。高さ180㎝×幅90㎝の掃き出しの障子の場合、組子は横方向に6等分する形で5本、縦方向に4等分する形で3本の配列となります。
横組障子
「横組(よこぐみ)障子」は、障子の基本にあたる種類で、「並組(なみぐみ)障子」とも呼ばれます。組子は、縦方向が荒組障子と同じ3本なのに対し、横方向は11~12本入る配列となります。障子枠の種類では、荒組障子と同様スタンダードなものになります。
横繁障子
「横繁(よこしげ)障子」は、横組み障子を変形させた種類の障子枠です。横方向の組子が横組み障子の半分の間隔と、かなり細かい配列になっているのが特徴です。茶の間や床の間の書院などに用いられる機会が多く、主に関東地方で好んで使用されます。
竪組障子
「竪組(たてぐみ)障子」は、横の組子を荒組障子と同じ5本として、縦の間隔を1/2にしてあるものを言います。荒組障子の場合、縦の組子は3本でしたが、竪組障子では8等分する形で7本になります。ちなみに障子の世界においては、「縦」より「竪」の字を用いることが多くなっています。
竪繁障子
「竪繁(たてしげ)障子」は、竪組障子を基本に据えた上で、縦の組子の配列をさらに半分の間隔に縮めた障子枠となっています。「竪繁」は、縦方向に細長い物を横に連続させることを指す言葉です。こちらの種類は、主に関西方面でよく使われます。
枡組障子
荒組障子を変形させたタイプで、縦と横の組子が正方形を形づくるように配されてある障子枠が、「枡組(ますぐみ)障子」になります。「無地障子」とも呼ばれます。モダンな味わいで和洋いずれのインテリアにも適する種類となっています。
吹き寄せ障子
「吹き寄せ障子」は、組子の配列にやや変化を持たせてある障子枠です。さまざまなパターンがありますが、間隔を詰めた縦(横)の組子複数本を一組とし、それらの組の間をやや広く取って組み込む形となっています。和風モダンな家の和室などに取り入れられるケースが多い種類です。
変わり組み障子
これまで紹介した障子枠は、シンプルに組子を縦横直線に配する形でしたが、「変わり組み障子」はより自由な配列がなされている点が特徴です。こちらもパターンはいろいろで、ひし形に組んだり、伝統柄や不規則な形にしたりと、デザイン性に重きが置かれています。配列が細かいため、DIYでの張替えにはあまり適しません。
形状・機能別の分類
水腰障子
下部に板が張られておらず、紙を全面に張り付けるタイプの障子を、「水腰(みずこし)障子」と言います。一般的に障子といってイメージするのは、こちらの種類でしょう。なお、「水腰」の「水」は「見ず」の当て字で、「腰」は障子下部の板を指す語になります。シンプルで、現代風のインテリアにもよくマッチします。
腰付き障子
障子における「腰」は、前述のように下部に位置する板を指します。「腰付き障子」は、この腰があるタイプの障子になります。腰板は240~360㎜程度の高さとなることが多く、600㎜以上となると、「腰高(こしだか)障子」とも呼ばれます。アンティークで見かけることが多い種類となっています。
雪見障子
「雪見障子」は、下半分がガラス張りとなっている種類の障子を指します。障子を閉め切っていても、外の雪景色を眺められることからこの名が付いています。中にはガラス手前に上下(または左右)に開ける小障子が付いているものもありますが、これらは「猫間(ねこま)障子」や「摺り上げ雪見障子」と呼ばれます。
額入り障子
「額入り障子」もまたガラス付きの障子ですが、こちらは中央部分に組み入れられている点が特徴です。額縁のような配置となることから、この名称が付けられました。腰付き障子に取り入れられることが多く、ガラスが縦長のものを「竪額(たてがく)障子」、横長のものを「横額(よこがく)障子」として区別しています。
太鼓障子
組子の外内両面に紙を張った障子を、「太鼓障子」と言います。一般的な障子は片面に組子が見えますが、太鼓障子の場合は紙のみが表面に見え、組子は影がのぞく形となっています。断熱性の高さが特徴で、寒冷地で多く活用されています。また、組子にホコリが溜まることがなく、掃除が楽という利点もあります。
猫間障子
「猫間障子」は先に少し触れた通り、雪見障子のガラスの上に、小さな障子を取り付けてあるタイプの障子です。小障子は、上下または左右に開く仕掛けになっています。もともと障子を閉めたまま猫が出入りできるように作られたもので、ガラスは後から付けられるようになったと言われています。
障子紙の種類
ここまで障子枠の種類について見てきましたが、枠だけでなく、そこに張られる紙にも多様な種類があります。張替えにあたっては、個々の紙の性質をある程度つかんでおくことが求められます。主な障子紙の種類と、その特徴を紹介しましょう。
手すき和紙
障子紙は、大きく「手すき」と「機械すき」の2種類に分けられます。このうち手すき和紙は、クワ科の植物である「楮(こうぞ)」を主な原料として、その繊維を一枚ずつ手作業で漉くことで作られます。
和紙は平安時代に日本独自の製法が確立され、以来障子紙を含むさまざまな用途で使われてきました。職人の手で作られるため量産に不向きで、価格も高価ですが、それだけに風合いに優れています。とりわけ楮の含有率が40%以上のものは品質が高く、含有率20~40%未満のものと比較して、強度にも優れます。
機械すき和紙
現在手すきの和紙に代わり一般的に流通しているのが、機械すきの和紙です。文字通り機械で漉くことで作られるため、量産できて費用も安く抑えられます。原料には楮以外に、パルプやマニラ麻などの繊維が用いられます。さらにいくつかの種類に分けられますが、以下でそれらについて解説します。
パルプ障子紙
80%以上がパルプから成るパルプ障子紙は、数ある障子紙の中でも、最も使われる率が高い種類です。価格も安価で入手しやすくなっていますが、強度は低めで比較的破れやすいという難点があります。劣化も早いことから、張替えはほぼ1年に1回のペースで行う必要があります。
レーヨン障子紙
レーヨン障子紙は、パルプを主原料としつつ、40%以上のレーヨンが配合されているものを言います。レーヨンは化学繊維に分類されますが、天然繊維に似た外観や質感があり、楮の性質にも近くなっています。それでいて手すき和紙より安価であり、入手しやすいという特徴があります。ホテルや旅館などの施設でもよく使われています。
レーヨン入りパルプ障子紙
上記のように、パルプに40%以上のレーヨンを配合したのが「レーヨン障子紙」ですが、レーヨン配合率が20~40%未満のものについては、「レーヨン入りパルプ障子紙」と呼ばれます。品質面ではレーヨン障子紙に若干及ばないものの、パルプ障子紙には勝ります。価格面もレーヨン障子紙とパルプ障子紙の中間に位置し、やはりマンションやホテル等の建物に多く使われています。